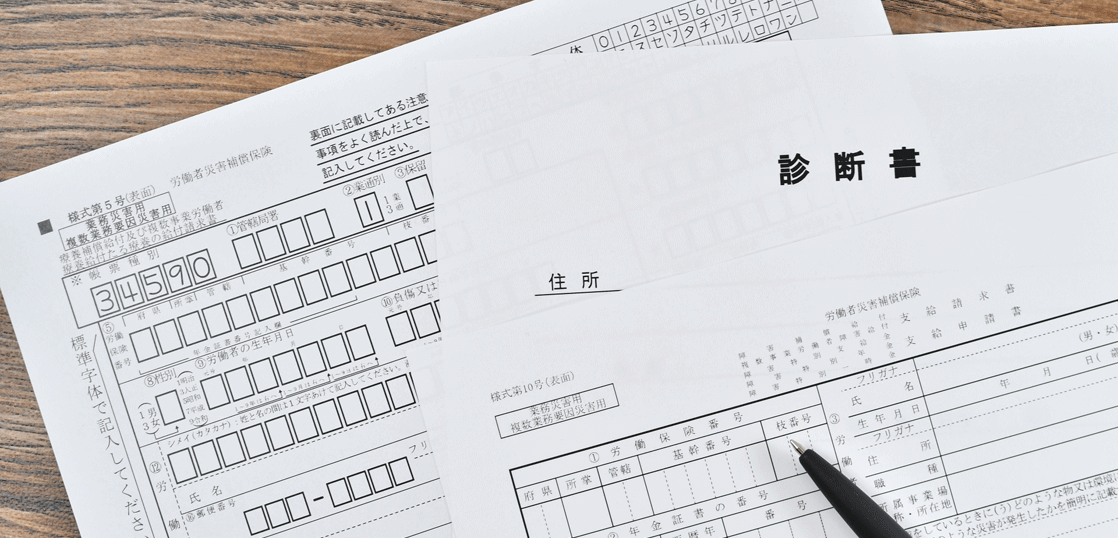労災給付申請をお断りする時の理由
一人親方の労災保険へ加入していても、要因や原因によっては業務災害認定を受けられない場合があります。
当団体では、労災事故の報告が上がってきて、内容確認、わからない表現等あれば電話でお聞きしてから、公的な申請書類にして会員様へ郵送しております。
ただし、業務災害認定をするのはあくまで「労働基準監督署」となりますので、当団体で判断することはできません。
しかしながら、これはどうしても無理が….と思う内容も少なからずあり、その際には理由を説明しお断りすることもございます。
この記事では、簡潔にわかりやすく貝瀬宇しています。
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には、特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。
厚生労働省 特別加入制度のしおり<一人親方その他の自営業者用>
請負元や工事現場名が無い
請負元とは当たり前ですが、一人親方や自営業者へ仕事を依頼する側です。
法人や個人事業主などの形態は関係なく、いうなれば「依頼する側」です。
例えば
A工務店からC親方が仕事を依頼された
A工務店=請負元
C親方=下請け
となります。
そして、一人親方等の労働とは「請負元と下請けの間に金銭の授受」があることを言います。
金銭の授受が無ければ仕事をしたとは言わないということです。
労働基準法定義(労働基準法第9条)
職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者労働組合法定義(労働組合法第3条)
厚生労働省 労働者について
職業の種類を問わず、賃金、給料、その他これに準ずる収入によって生活する者
このように、仕事の対価として「賃金」が支払われる方が「労働者」となるわけです。
仕事を依頼する方や組織から、その指示及び指揮によって仕事を行い、対価としてお金(賃金)が支払われるという図式がはっきりしています。
さて、一人親方の労働性と、労働者の労働性は全く違いますよね。
一人親方は、基本だれの指揮下にも束縛されず(社会通念上の事を除く)自由に働くことができま。
ただし、その自由が上の「一人親方として働くのか、労働者として働くのか」と切り分けが必要となります。
以下の場合は、一人親方としての働き方(労働性)ではないため、労災保険の給付が受けられなくなります。
- 自分の家や事務所、作業場などを自分で修理、建設、設備等行った
- 親戚や知人から頼まれて、作業を行った
- 友人からのお願いで、作業を行った
- 請負元や工事現場名もない
- 対価として賃金の授受がない
これらは、使用する者(依頼する元)がはっきりしないため、また契約書等もないため労働性が無いと判断されてしまうからです。
業務災害として給付を受けるときは、必ず「請負元名と現場名」が必要となりますのでご注意ください。
業務災害の証明者がいない
証明者とは、事故を目撃した方もしくはその事故が本当に起きたことを証言してくれる方のことを言います。
自分で仕事中の事故です、と言ってもそれが本当に業務中だったのかを労働基準監督署側では判断することが出来ませんよね。
嫌な話ですが、自作自演もできてしまうだけでなく、、過去に詐欺罪として刑事事件になった例もあります。
ですから、第三者の目撃者もしくは事故発生証言できる保証人が証明者となるわけです。
あってはならないことですが、万が一虚偽があった時には、保証人も連体責任として訴訟対象になることもあります。
一人親方は、実際は一人で工事を行う場合も多いかと思います。
一人で現場で仕事をする際は、必ず第三者へ「いつ・どこで・なにを・だれから」を告げて仕事を行ってください。
第三者行為災害(第三者が要因での業務災害)
この第三者行為災害に多いのは「交通事故」です。
交通事故は通勤災害としてのケースが非常に多いのですが、あくまでも「通勤途中」としてですので、これは通勤としての経路ではないと判断できる内容であれば、災害給付を受けることができません。
また、通常は就業の場所から逸脱した場所へ寄った場合には、通勤の中断となり、その後家に帰るとしても通勤途中として判断されないため注意が必要です。
ただし、厚生労働省で逸脱した経路の例外が認められていますので、ここに掲載しておきます。
1.日⽤品の購⼊や、これに準ずる⾏為
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 通達
2.職業訓練や学校教育、その他これらに準ずる教育訓練であって職業能⼒の開発3.向上に資するものを受ける⾏為
4.選挙権の⾏使や、これに準ずる⾏為
5.要介護状態にある配偶者、⼦、⽗⺟、配偶者の⽗⺟並びに同居し、かつ、扶養している孫、ここが変更点祖⽗⺟および兄弟姉妹の介護(継続的に、または反復して⾏われるものに限ります。)
※平成29年1月1日より5.の「同居・扶養要件が撤廃されました。これにより、同居・扶養していない孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護のため、合理的な通勤経路を逸脱・中断した場合も労災補償対象になりました
忘れていいけないのは、就業場所内での交通事故です。
仕事仲間だからと警察を呼ばず事故証明もないケースがあります。
これは第三者行為を証明するものが無いため、災害給付ができない場合もあります。
必ず警察を呼んで、事故証明を取っておいてください。
これはもう言うことはないかと思いますが、仕事上での喧嘩や飲酒しての災害は絶対に認められません。
加入間への病院が原因
政府労災には、民間のように「病気」(以下疾病という)に関する告知義務はありません。
しかしながら、従前にかかっていた疾病を要因として、業務中に起きた災害に関しては、給付の対象とはなりません。
一人親方は、仕事の選択することが雇用されているものと違って拒否や選択が自由にできます。
つまり、疲れて仕事ができない、乗り気じゃない、もっと言えばやりたくないと思ったら、単純にやらなくてもいいわけです。
ですから、通常はきつい業務だとしても、体調が優れなければ休暇は自由という基本原則により「疾病」は起きないという考え方になりがちです。
さらに疾病に関しては自己管理でというのが厳しいですが現実です。
熱中症などは問題ありませんが、過重労働を起因とした「疾病」は無いと考えられます。
一人親方は「社長」と同じですから、自分の身は自分で管理し、守ることが最優先です。
まとめ
このように、一人親方は「自由」と引き換えに「自己責任」が重くのしかかっています。
ただ、それ以上に自分の能力でいくらでもお金を稼ぐことも可能ということでしょう。
では、最後に業務災害として認められない可能性を今一度確認してみましょう。
- 請負元・工事現場名が無い
- 災害を証明、または事故発生を保証する方がいない
- 通勤途中でも、逸脱した場所へ寄ってしまった
- 事故証明ができない
となります。
ただし、自己判断で「むりだろうな」と考えないで先ずは必ず相談してください。
西日本労災一人親方部会の会員の方は、必ず事故報告をお願いいたします。
西日本労災一人親方部会の事故報告はこちらです。
↓
労災事故報告はこちらから
大学卒業後、今は無きXEROXで営業力を発揮。コンテスト受賞歴は多数。
37歳の時人生観を変える大きな出来事に会い会社員を辞め起業。IT、建設、金融、海事や伝統工芸など様々な事業を展開し経験を重ねる。
各種業界経営者からのセミナー依頼を多数受け、講師として活躍。厚生労働省承認特別加入団体の運営を開始。
相談者に耳を傾けるため産業カウンセラーの資格を得て労災関連全般の業務を執り行っている。
–自己紹介–
人見知りという概念が欠落しているらしく、初対面でもすぐ仲良くなります。
相手の気持ちに入り込みすぎて疲れちゃうことも多々あり。
人の笑顔が大好物。嫌いなものは、なぜかシイタケ。細かく刻んであっても見つけられる得意技。
趣味は釣り全般・ギター・ガーデニング・料理・DIY・車・喫茶店回り、船の操船などなど。
多趣味すぎて時々自分でも困ることあり。
釣りに関しては遊漁船経営までしてしまったという変な人です。
座右の銘は「失敗は行動している証」
失敗した人を「ほら見たことか!」という人ほど何もしてないですよね。