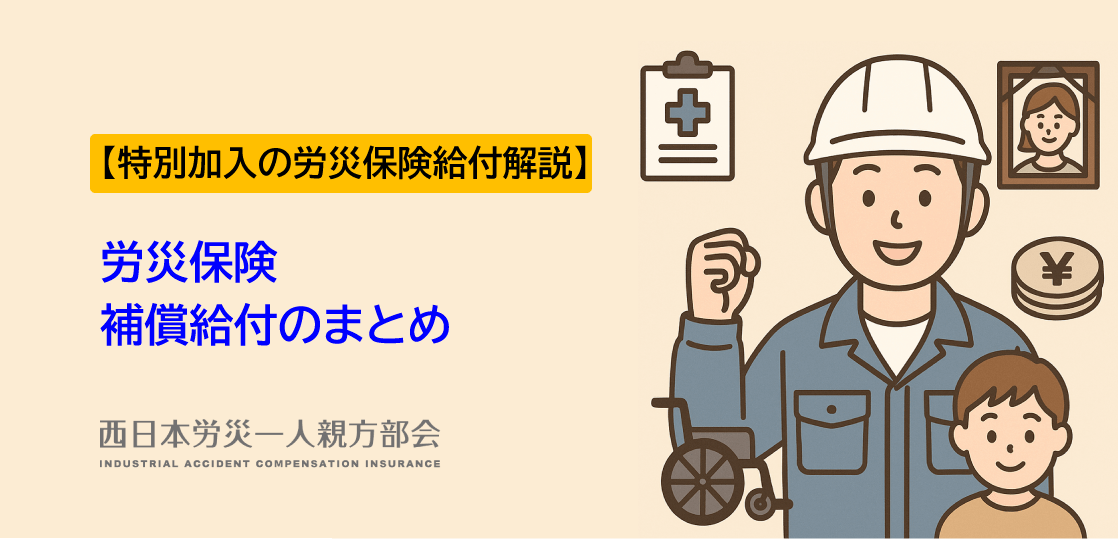一人親方や中小事業主でも、労災保険に「特別加入」することで、ケガや病気、後遺障害、万が一の死亡事故まで、幅広い補償を受けられることをご存じでしょうか?
特別加入の労災保険へ加入をするだけで、業務中のケガや事故に対するさまざまな給付制度が自動的に適用されます。
しかし、「どんなときに」「どんな補償が」「いくら支給されるのか」は、意外と知られていないのが現実です。
この記事では、特別加入で受けられる労災保険給付の全体像をわかりやすく紹介します。
各給付の詳しい内容については、別の記事で個別に解説していますので、気になる補償があればあわせてご覧ください。
そもそも労災保険って何なの?
労災保険とは、労働者を業務災害から経済的に支援(守る)ための、とても大切な「社会保険制度」です。
日本国内の民間が運営する保険制度では、保険者と契約者、被保険者と受取人に区分けされています。
政府が執り行う保険制度には、保険者と被保険者しかなく、受取人は被保険者となります。
| 呼び名 | 特別加入の労災保険 | 民間の生命保険等 |
|---|---|---|
| 保険者(ホケンジャ) | 日本政府(厚生労働省) 保険制度を運営する者 | ○○生命保険株式会社など 保険商品の設計から保険金支払いまですべてを行う者 |
| 契約者(ケイヤクシャ) | 被保険者本人・加入者 | 保険契約の支払いからすべての責任を負うもの |
| 被保険者(ヒホケンシャ) | 被保険者本人・加入者 | 保険の補償をかけている方 |
| 受取人(ウケトリニン) | 加入者もしくはその家族や親族 受取人という呼び方は基本しない | 被保険者に何かあった時に保険金を受け取るもの |
労災保険は、業務を行うことにより傷病(ケガや病気)になり、病院へ治療にいったり、後遺障害になったり、介護状態や死亡したときなど、政府が経済的支援をする制度です。
労働に特化した(業務起因性)保険制度ですから、一般生活において起こる傷病の補償は、健康保険制度を利用します
労働に特化した保険制度ですから、業務災害における治療に関しての自己負担は0円です。つまり、病院に行って治療を受けても、支払いが無いということです。
健康保険の自己負担は3割ですから、労働に対して政府は、手厚い補償を提供しています。
特別加入って?
特別に加入できる労災保険制度だから、特別加入の労災保険。
そもそも、労災保険は労働者を守るもので、労働者で無いものは、加入したくても加入できません、ということです。
労働者か否かの判断基準は、他の章でも説明していますが、労働基準法第9条の「労働者の定義」を基に判断しています。
労働基準法 第9条 労働者の定義
職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
この法律では「事業や事務所に使用され、賃金を支払われる」となっており、一人親方やフリーランスのように、「使用されていない」そして「賃金は支払われていない」方は、労働者とは言わない、いわば非労働者なのです。
そもそも、労働者ではない=労働をしていない=労災保険には加入できませんでした。
ただし、実態として「働かないでどうやって生活するの?」となりますから、「事業や事務所に使用されていない」はそのままに、「賃金ではなく、出来高で支払われる者」でも、特別に労災保険へ加入できるようにした制度だから「特別加入の労災保険」とした社会保険制度です。
労働保険とは何が違うの?
社会保険制度の強制加入保険である「労働者災害補償保険」のことを、労働保険と言います。
そして、この労働保険は、2つの社会保険制度の総称です。
- 労災保険
- 雇用保険
雇用されている方は、この2つの保険である「労働保険」へ、強制加入です。
つまり、雇用契約を結び(労働契約やパートアルバイト契約も同等)労働の対価として賃金(時給や週給や月給など)を受け取れば、自動的に「労働保険」へ加入しています。年間100日未満や週20時間未満の労働など様々な要件もありますが、基本的には賃金労働の方は、1分でも働けば「労災保険加入」は必須となり、週20時間以上の労働時間の拘束があり、且つ31日以上の労働見込みがある場合は「雇用保険」も必須加入となります。
雇用入れし、1分でも労働するなら「労災保険」は必須加入です。雇用保険は、週20時間以上の労働があり、31日以上満たした時点での加入手続きで問題ありません。労働契約書(雇用契約書など)に時間的・期間的な契約事項がある場合は、それに沿って労働保険加入手続きを行いましょう。
労働保険の支払い義務者はだれなのか
労働保険の支払い義務者は「雇用主」なので事業主です。
雇用されている者は「労働者」ですから、直接労働局等へ支払いをすることはありません。
また、保険料の負担割合は
- 労災保険 事業主が全額負担
- 雇用保険 事業主と労働者で負担
このように、労働保険のうち「労災保険は事業主全額負担」となり、雇用保険は業種によって差はありますが「事業主6割~7割負担・労働者4割~3割負担」となります。
一人親方やフリーランス・自営業者は?
事業主と同じですから、労災保険は全額自己負担で、特別加入の労災保険からのみ、加入が可能です。
もちろんのこと、一人親方やフリーランス、自営業の方は、組織体に雇用されていませんので、雇用保険には加入できません。
雇用保険とは、労働者が失業したときや働けなくなったときの生活と就労を支える公的保険制度ですから、雇用されていない一人親方は雇用保険へ加入することができません。
特別加入の労災保険にはどんな補償があるの?
特別加入の労災保険に加入するだけで、様々な補償給付制度を受ける権利が生まれます。
では、代表的な補償給付制度を、各章(ブログ記事)に分けて詳しく説明していきます。
興味がある補償給付をクリックしていただき、ぜひとも内容をご覧ください。
一人親方の労災保険各種補償給付一覧
詳しい解説の記事へ遷移します。知りたい労災保険補償給付制度をクリックしてください。
知りたい労災保険補償給付制度をクリックしてください。
- 療養補償給付・療養給付はこちら
- 休業補償給付・休業給付はこちら
- 障害補償給付・障害給付はこちら
- 傷病補償年金・傷病年金はこちら
- 遺族補償給付・遺族給付はこちら
- 葬祭料・葬祭給付はこちら
- 介護補償給付・介護給付はこちら
まとめ
だれもが自分は大丈夫!自分は起きないし問題ないと思ってしまうのは仕方がないのかもしてません。
また、支払ったのに戻りが無い、だから無駄だと思っている方も多くいらっしゃいます。
しかし、仕事中のケガや病気(熱中症など)は、自ら「起こしたくて起こしている」わけではなく、その時は突然やってくる、ということを再認識して欲しいのです。
また、業務災害での治療に際しては、「国民健康保険は使用できない」ため、労災保険に加入していないと治療にかかった費用が全額自己負担となってしまいます。
万が一国民健康保険を使用した場合は、健康保険法上の違反であるばかりか、その後の追加費用(例えば休業のときの補償や、後遺障害のときの補償など)が一切受けられなくなります。
仕事中に自分の身に何かあったとしたら、自分ばかりか家族や仕事仲間、そして元請けにも大変な負担を強いることになりかねません。
一人親方やフリーランスなどの方々は、「特別加入の労災保険」へ加入は必須ともいえるでしょう。

西日本労災一人親方部会では、労災保険にかかわるすべての申請書類作成を無料で代行しています。
加入や脱退においては「特別加入承認団体」を通じ申請します。
ですから、ほとんどの労災保険取扱団体では、申請書類の作成を代行しています。
特に、労災事故が発生したら、加入している団体や組合にすみやかに労災事故報告を行いましょう。
西日本労災一人親方部会は、加入から脱退、労災事故報告の連絡が入れば即座に対応しています。
専門家がスピーディに、しかも「無料」であなたをサポートします。
万が一に備えるなら、西日本労災一人親方部会で安心安全なサポートを受けましょう。
大学卒業後、今は無きXEROXで営業力を発揮。コンテスト受賞歴は多数。
37歳の時人生観を変える大きな出来事に会い会社員を辞め起業。IT、建設、金融、海事や伝統工芸など様々な事業を展開し経験を重ねる。
各種業界経営者からのセミナー依頼を多数受け、講師として活躍。厚生労働省承認特別加入団体の運営を開始。
相談者に耳を傾けるため産業カウンセラーの資格を得て労災関連全般の業務を執り行っている。
–自己紹介–
人見知りという概念が欠落しているらしく、初対面でもすぐ仲良くなります。
相手の気持ちに入り込みすぎて疲れちゃうことも多々あり。
人の笑顔が大好物。嫌いなものは、なぜかシイタケ。細かく刻んであっても見つけられる得意技。
趣味は釣り全般・ギター・ガーデニング・料理・DIY・車・喫茶店回り、船の操船などなど。
多趣味すぎて時々自分でも困ることあり。
釣りに関しては遊漁船経営までしてしまったという変な人です。
座右の銘は「失敗は行動している証」
失敗した人を「ほら見たことか!」という人ほど何もしてないですよね。